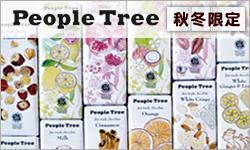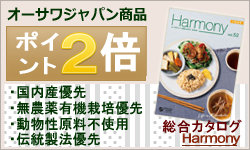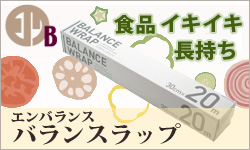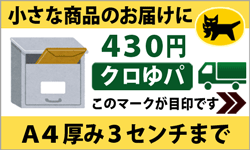粟国島近海の海水100%原料、ミネラルバランスに優れたおいしいお塩 【天候により、入荷にお時間かかることがあります】 粟国の塩(あぐにのしお) 160g <スタンドパック>|沖縄海塩研究所
- アレルギー
- イチ押し
販売価格
¥
648
税込
0104



 注目のキーワード:
注目のキーワード: